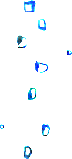
「今何してんのー」
電話越しに響いた彼の声は珍しく随分ご機嫌だった。
「レポートしてる、明日提出だから」
「ふーん、なー会いたい」
「今から?無理だよレポート全然終わってないもん」
「いーじゃんレポートとか」
「無理だって、出さないと単位ないもん」
「ひっで、俺より単位なわけ?」
「単位だよ」
「なー来てよー」
「しつこいよ」
「あーもーつめてーな」
プツリと乱雑に切られた電話からは無機質な電子音が流れるだけで、私の「え」という間抜けな声は静かな部屋に妙に響いた。切られる直前の彼の声色は、ご機嫌だった第一声とは別人のように冷たかった。怒ったんだろうか、なんて私が感じる必要のない不安で胸が埋め尽くされていく。慈郎はひどく気まぐれだ。こんな風に機嫌よく近付いてきても平気で手のひらを裏返したように冷たくなるし、一切の興味をなくしたように素っ気なくなる。私は私で慣れれば良いものを次の日まで、下手すれば一週間も気にするハメになる。当の慈郎は次の日には私に電話をかけたことすら忘れてしまっているというのに。
当然、もうレポートなど頭に入らない。やっと指が乗ってきたところだったのに、もう今日はこれ以上進みそうにもない。慈郎の「つめてーな」という言葉がぐるぐると胸の中で回り続けるばかりで、資料に借りてきた本の内容は無理やり読み進めようが一文字も頭に入ってこない。
連絡など来ているはずもないのに携帯が気になって画面をスライドさせると、「22:23」という時間がやたら目に付いた。今から用意をしても終電までは時間がある。慈郎の家に行くには十分な時間だ。ただ、行ってしまうと帰ってこられるか分からない。なんて、悩んでいられるほど十分な時間ではない。慈郎の連絡のタイミングはいつも絶妙なのだ。
これ以上自分に言い訳するのはそれこそもう時間の無駄だ。どうせ私は彼の家に向かってしまうのだから。諦めて化粧ポーチを掴んで足早に洗面所へ向かった。
ドアを開け私を迎えた慈郎は先ほど自分が言い捨てた言葉など忘れているかのようにあっけらかんとした顔で「じゃん」なんて言いやがった。さっきのたった一言に振り回されて思い悩んだ時間がいかに無駄であったかを思い知る。いつものことだ。
「なになにまじで来てくれたの」
「あんな頼み方されたら何かあったのかと思うじゃん…」
「あはは、そーいうわけじゃねーけど」
「何それ…じゃあ帰る」
「わーうそうそ、来てくれて嬉しいって」
抱き寄せられた腕の中はワックスの匂いや煙草みたいな食べ物みたいな外の匂いを帯びたままで、遊びの雰囲気を漂わせている。未だシャワーを浴びていないのだろう。帰ってきたばかりなのだろうか。私といない時慈郎が誰と何をしているのか、私はその雰囲気を感じ取ることはあっても確実に知りえることはない。詮索出来るような間柄でもなければ、適当に誤魔化されてもそれを責められる関係でもない私には真実を知る方法がない。「いー匂い」と言いながら慈郎が私の旋毛の辺りに鼻を擦り付ける。そりゃあそうだろう。私は慈郎と違って今日はレポートを終わらせるために早めに帰宅してさっきシャワーを済ませたばかりだし、日付が変わる前にはベッドに入るつもりだった。私がいくら綿密なスケジュールを立てようが、慈郎によってそれは簡単に狂わされる。慈郎の服の匂いが移ってしまいそうで体を引きかけたけど、どうせまた後でシャワーを浴びることになるだろうと思うとどうでもよくなった。明日からは計画的に生きよう、そう何度心に誓おうと慈郎の前では全部無駄だ。
慈郎が私のブラウスの裾から手を潜り込ませてきたので流石にぎょっとして、慈郎の肩を思い切り押し返す。外だよ、と少しも遠慮のない慈郎の右手を払い除けると、「ひでえ」と言って慈郎はへらへらと笑った。ひどいのはどっちだ。
分かっていたけど部屋に入るや否やベッドになだれ込んで、慈郎は私のブラウスのボタンを外すこともなく上から引き抜くと、自分も乱雑にTシャツを脱ぎ捨てた。足元でぐしゃぐしゃになっているブラウスは一応慈郎の前では着たことのない新しいものだ。そんなことを気にする人間じゃないことは分かっているのに、私も大概懲りない。5回連続同じTシャツで会い続ければ流石の慈郎も「ちょっとは気にしろよ」とか思ったりするんだろうか。試してみたいような気もするけど、絶対にしない。私はこの人の前で失敗することを何よりも恐れている。
「痛い?」
「…ううん」
「気持ちいい?」
頷きながら自分の愚かさに絶望する。「すげー好き」と唇を塞がれてやっぱりどうでもよくなる。どうせならいつもみたいに適当に扱って欲しい。優しくされると余計に息が詰まる。
「やることやったら即寝ですか」
私のぼやきに少しも気付くことなく慈郎は眠りこけている。無防備な寝顔は少しもその残酷さを思わせない。
会いたい、とか好き、とか別に意味はないんだって分かってる。
私が今都合のいい女というだけで別に私でなくたっていいのだ。彼の退屈を凌ぐための方法や人間はいくらでも存在する。少なからず好意を持たれているんだろうけど、別にめちゃくちゃ特別ってレベルじゃない。それぐらいしか分からない。
少し冷静さを取り戻すと、途中で放りだしたレポートのことが気になり出して、タクシーでもいいから帰ろうか、なんて考えながらどこかで丸まっているであろうブラウスを探した。
ベッドの上をがさがさと動き回る私の気配が気になったのか、慈郎は寝転んだまま手探りで私の腕を掴むと、自分の方に引き寄せた。
「…帰んの?」
「…レポート終わってないし」
「電車ないじゃん」
「タクシーで…」
「んー金もったいないよ」
「でも…」
「…俺の原チャ使うなら鍵鞄の中…」
引き止めてくれるわけではないのか。何を期待したのか泣きそうになるほど落胆している自分がいる。何がタクシーだ。きっと私は少しでも引き止められればここに留まっただろう。こうやっていつも自分で墓穴を掘る。帰りたいのなら慈郎の言うとおり慈郎のバイクを借りて家に帰ってレポートの続きをすればいい。帰りたくないのなら最初から諦めて慈郎の腕の中で眠ってしまえばいいのに、こうやって慈郎を試すようなことをしては自分の首を絞めて行く。「帰る」なんて言ってしまったから、私は朝起きた慈郎に「まだいたんだ」と言われてまた一週間落ち込み続けるなんて事態を避けるために、いかにも自立していてマイペースな女を装ってさっさと帰らなければいけない。バイクを借りて帰って、それを返し終えればまたしばらく慈郎からの連絡はないのだろう。こうやって会ってしまうから次を待ってしまう。嫌ならやめればいいのに、私はどうにも慈郎のように単純には生きられないらしい。
あれだけ「会いたい」なんて言っていたくせに。といっそ責めることが出来れば楽なのに。今日一日のやり取りを思い返せば、その怒りすら無駄だと分かってしまう。まともな会話なんてなかった。性急なセックスに申し訳程度の甘い言葉。それが私たちの全てだ。
慈郎に言われたとおり彼の小さな鞄の中を覗くと、大きなドナルドダックのキーホルダーが付いたバイクのキーが無造作に突っ込まれていた。大学生の鞄とは思えないサイズのメッセンジャーバッグには財布に携帯と数本のペンがペンケースに仕舞われることもなくレジュメのようなものに包まって入っている。身軽な彼は常に無駄なものは持ち歩かない。私も、必要にはなれなくとも重荷にはならないよう細心の注意を払ってきた。だからこそ中学高校と続いているこの不安定な関係が未だに切られていないのだという無駄な優越感や達成感があったりもする。
バイクのキーを取り出して、慈郎のあどけない寝顔を背中に静かに部屋を出る。バイクに乗ってしまえば涼しい夜風や疎らに付いた街の明かりがいくらか清々しい気分にさせてくれる。いくらか頭がスッキリすると、酷く喉が渇いていたことを思い出して、コンビニの前にバイクを止めてポカリスウェットを買った。
グビグビと音を鳴らして思い切り飲み込むと、乾いて粘ついた喉に独特の心地よい甘さが冷たく染み渡った。思わず慈郎の「つめてーな」という言葉が蘇る。
私は彼ほど冷たい人間を知らない。いつか彼を暖めてくれる人間が現れるのだろうか。幼ながらにそれが自分であったら、なんて淡い希望を抱いていた頃もあるけど、あまりの手ごたえのなさにその思いは早々に散った。いつからだろう。そんな人間は一生現れなければ良いと思うようになったのは。それも、私が切り捨てられてしまうことへの不安からではなく、恵まれた彼の欠陥を垣間見て見下げることで安心してしまうような醜い嫉妬へ変わってしまったのは。
彼に惹かれるのと同じだけ、彼の消滅を願わずにいられない。
in the stomach.